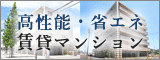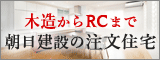・to-Be-N(トゥービーエヌ)
【概要】
・鉄筋コンクリート造
・地上3階建 1K(3)・1LDK(2)・オーナールーム
・横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」駅より徒歩7分
皆さまこんにちは(・∀・)
戸部町の現場日記、最後の更新となりました。
本日は、工事が始まってから竣工に至るまでを振り返っていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします![]()
to―Be―N 完成した物件の様子
to―Be―Nは、
竣工までの工事日数:232日、現場で働いた職人さんの延べ人数:1621人で
完成を迎えることができました( ゚∀゚ )
また、工事中は近隣の方をはじめ多くの方にご迷惑をおかけいたしました。
そして多くの方のご協力とご理解のもと、無事に竣工を迎えることができました!!
本当にありがとうございました。
引き続き現在着工中の物件もよろしくお願いいたします![]()
・鉄筋コンクリート造賃貸マンション│完成物件のご紹介
皆さまこんにちは!
では、現場日記を更新いたします。
横浜市西区戸部町、7月中旬に完成見学会を行いました!!
本日は完成しました物件のご紹介をさせていただきます(・∀・)
建物名は「to―Be―N」。シンプルデザインの館銘板が付きました![]()
外観の一部はコンクリート打ち放しでございます!!かっこいいですよねえ
エントランスのご紹介です。
当物件は1K・1LDKの2タイプでございます( ゚∀゚ )
まずは1Kのご紹介。
続きまして、1LDK。
新築ホヤホヤ素敵な賃貸マンションが出来上がりました!!
次回は最後の現場日記となりますので引き続きよろしくどうぞ![]()
・【完成見学会開催】ご来場いただきありがとうございました!
皆さまこんにちは(・∀・)
毎日毎日暑いですね・・・溶けそうです・・・
皆さまも熱中症にはくれぐれもお気をつけください・・・
では!戸部町の現場日記を更新いたします__![]()
告知通り、7月17.18日の2日間で完成見学会を開催いたしました!!
おかげさまでお引渡し前に【満室御礼】です。
今回もコロナウイルス感染予防対策を徹底した上での開催となりました!!
1階エントランス部分に受付を設けて、さらに工事の歩みや弊社の施工実績資料を掲示させていただきました(^_^)
鉄筋コンクリート造の地上3階建、自宅併用賃貸マンション。
新築ホヤホヤの物件をお引渡し前にご覧いただきましたよー(*゚∀゚)
今回の2日間の完成見学会。
おかげさまで16組のお客様にご来場いただきました![]()
![]()
暑い中、会場にお越しいただき誠にありがとうございました!!
ではでは、次回のブログもよろしくどうぞ。
あ!近日、やるぞうTVにて見学会の様子を動画でご紹介しますのでおたのしみに!!
・【お知らせ】7月17(土).18(日)の2日間で完成見学会を開催いたします
皆様こんにちは!
では!現場日記を更新いたします__![]()
戸部町4丁目マンション、無事に足場解体が終わりました!!
バルコニーの手摺にご注目していただくとー・・・「現場見学会近日開催!」
ここでお知らせ(・∀・)
7月17(土).18(日)の2日間で完成見学会を開催いたします![]()
只今、完成に向けて工事が進んでおりますよー!!
共用廊下や階段、そしてバルコニーには、長尺シートが貼られました![]()
![]()
長尺シートは、正式には防滑性ビニル床シートといいます。
滑らず、掃除の手間がかからず、また遮音効果もある床専用のシートになりますよ。
当物件のバルコニーは、木目調デザインの長尺シートが貼られています( ゚∀゚ )
室内のお部屋も出来上がってきましたよー!!
この続きは、完成見学会にて![]()
・
賃貸住戸は1K29?と十分な広さを確保し、かつ収納付きの小上がりを設け、より住みやすさにこだわりました。
・
また、1LDKも2種類の間取りを用意し、それぞれ収納やワークスペースなどこだわり満載です。
ご興味のある方はぜひ!ご来場お待ちしております![]()
![]()
![]()
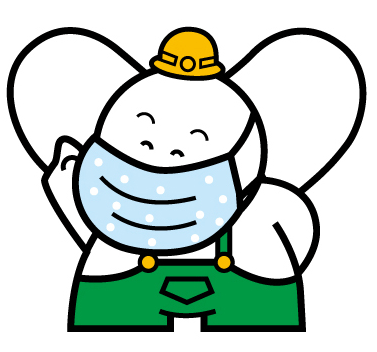
現地までのアクセス。住所は【横浜市西区戸部町4―165】です。
![]() :横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」駅より7分 / 京急本線「戸部」駅より10分
:横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」駅より7分 / 京急本線「戸部」駅より10分
・足場の解体作業が行われました
皆さま( ノ゚Д゚)こんにちは
では!戸部町の現場日記を更新いたします__![]()
当現場はなんとー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
足場の解体作業が行われました!!
上から順に解体作業を行っていき・・・
下にいる職人さんへ・・・
そして、トラックへ積んでいくという作業を繰り返し行っています!!
華麗なる連携プレ?です。見ていて気持ちよかったです(笑)
建物内では、タイルの酸洗いを行っている職人さんが!!
表面だけでなく、目地もきれいになるので仕上げとして行う作業になります(^ω^)
ちなみに。
足場解体作業は、先日に行われました構造見学会の翌日から始まりました!!
また、7月17(土).18(日)の2日間にて完成見学会を開催いたしますので
ぜひぜひ会場に足をお運びくださいませ![]()