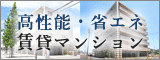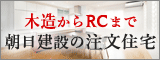躯体工事の最近のブログ記事
☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|5階立上りコンクリート打設(上棟・天端ポインター)
皆さま、こんにちは。
ついに5月も最終週となりました。
梅雨、そして暑い時期が近づいてきていますので、
エアコンの試運転など今できる準備をしておきましょう!

さて、前回は5階のスラブ配筋の様子をお伝えしました。
(☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|5階スラブ配筋(スペーサー・ダブル配筋))
今回は5階立上りコンクリート打設の様子をご紹介いたします!
▲生コンを運ぶミキサー車、生コンを上階まで圧送するポンプ車が前に停まっています。
上棟(※)まで「配筋工事・型枠の建て込み」→「コンクリート打設」を繰り返してきた当物件。
今回の5階立上りコンクリート打設でついに上棟となります!
※上棟
建物の基本構造が完成した状態のこと。
造りによって上棟と呼ぶ状態は異なるが、
鉄筋コンクリート造では屋根部分のコンクリート打設の完了時であることが多い。
今回コンクリートを流し込んでいくのは建物の一番上、つまり屋上部分です!
打設の流れは今までと同様で、打設用ホースをコントロールする職人さんに、
生コンにバイブレータで振動を与える職人さんなど、色んな職人さんたちの連携プレーが見られました。
▲重い打設用ホースはホースにつけたロープで操ります。
細長い棒のようなものがバイブレータ、生コン内の不要な空気を除去します。
今回注目したいのが上の画像の端に映り込んでいる天端(てんば)ポインターです!
こちら、実は屋上の打設の時にしか見られないレアアイテムなんです。
▲天端ポインター。
白色や青色など様々な色のものがあります。
天端ポインターが屋上の打設時に設置される理由は「勾配」にあります。
屋上は建物の中で最も雨の影響を受けやすい部分です。
屋上が平らだと水が溜まり続けてしまい、建物の劣化が進行しやすいだけでなく、
建物内部への浸水にもつながってしまい、雨漏りまでも引き起こしてしまう可能性もあるんです。
雨による建物の劣化を防ぐために、屋上は水が流れやすいように勾配をつけて造る必要があります。
天端ポインターを各箇所に応じた高さに合わせて設置し、
これを基に打設を行うことで勾配をつけることができるんです!
▲あちこちに設置された天端ポインター。
それぞれがその箇所に応じた高さに合わせて設置されています。
天端ポインターを目印に打設を進めていき、
その後は今までの打設と同じようにトンボや鏝で均して仕上げていきます。
そして打設完了の様子がこちらです!
無事上棟となりました!
上棟を迎え、これで躯体工事(建物自体を造っていく工事)は完了です。
次回からは内外装工事の様子をお届けしていきますよ。
それでは今回はこのへんで!
次回の更新をお楽しみに!
【完成予想パース】

◇物件詳細
◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら
◇賃貸経営をご検討の方はこちら
◇注文住宅をご検討の方はこちら
◇見学会にご興味がある方はこちら
☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|5階スラブ配筋(スペーサー・ダブル配筋)
皆さま、こんにちは。
ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか?
お休み中の過ごし方は十人十色、その人らしさが出ていて話を聞くだけでも面白いです。
連休明けで仕事や学業に調子が出ない方々もいると思いますが、一緒に頑張りましょう!

さて、前回は4階立上りコンクリート打設の様子をお伝えしました。
(☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|4階立上りコンクリート打設(CD管(合成樹脂可とう電線管)))
今回は5階のスラブ配筋の様子をご紹介いたします!
上棟(※)となる5階まで「配筋工事・型枠の建て込み」→「コンクリート打設」の流れを繰り返していきます。
前回はコンクリート打設を行ったので、次は配筋工事・型枠の建て込みとなります。
※上棟
建物の基本構造が完成した状態のこと。
造りによって上棟と呼ぶ状態は異なるが、
鉄筋コンクリート造では屋根部分のコンクリート打設の完了時であることが多い。
取材当時、現場ではスラブ配筋が行われていました!
スラブ配筋はスラブ=上階の床と下階の天井になる構造体の上に配筋を行う作業です。
4階の天井かつ屋上になるスラブに鉄筋を組んでいきます。
何やらスラブの上に鉄筋ではないものを設置している職人さんがいました。
こちら、スラブ用のスペーサーを設置している職人さんでした!
スペーサーはかぶり厚さを確保するために型枠やコンクリートと鉄筋の間に差し込みます。
かぶり厚さは鉄筋の外端とそれを覆うコンクリートの外側表面までの最短距離のこと。
コンクリートの経年変化によって中の鉄筋まで腐食してしまうのを防ぐため、かぶり厚さが規定されています。
▲職人さんがスペーサーを設置する様子
▲スラブ用のスペーサーを設置することで、一定のかぶり厚さを確保します!
上の画像で気づかれた方もいるかもしれませんが、
スラブ配筋では鉄筋が二重になるような形で配筋するダブル配筋を行っています。
上端筋(上部の鉄筋)と下端筋(下部の鉄筋)を二重に配置していますよ。
そして鉄筋同士が交差するところは結束線(※)で結んでいきます(=結束)。
ハッカーという道具を結束線の先端に引っ掛け、くるくる廻して結束していきます。
※結束線
鉄筋同士を緊結するために用いる鉄線のこと。
加熱した後に徐々に冷やす「焼きなまし」という処理が行われており、柔らかい鉄線になっている。
▲爪のような形の道具がハッカー、銀色の線が結束線。
職人さんが見事な手さばきで素早くどんどん結束していました!
着々とコンクリート打設に向けて準備が進んでいました。
次回はいよいよ5階立上りコンクリート打設、上棟となります!
それでは今回はこのへんで!
次回の更新をお楽しみに!
【完成予想パース】

◇物件詳細
◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら
◇賃貸経営をご検討の方はこちら
◇注文住宅をご検討の方はこちら
◇見学会にご興味がある方はこちら
☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|4階立上りコンクリート打設(CD管(合成樹脂可とう電線管))
皆さま、こんにちは。
もうゴールデンウィークですね!
ゴールデンウィークは映画業界の宣伝用語として生まれた言葉だそうです。
ぜひGWは映画を観てみたりしてみてくださいね。
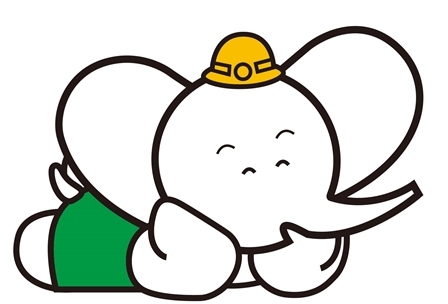
さて、前回は4階の型枠工事の様子をお伝えしました。
(☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|4階型枠工事(型枠支保工(パイプサポート)))
今回は4階立上りコンクリート打設の様子をご紹介いたします!
上棟(※)となる5階まで「配筋工事・型枠の建て込み」→「コンクリート打設」の流れを繰り返していきます。
前回は配筋工事・型枠の建て込みを行ったので、次はコンクリート打設となります。
※上棟
建物の基本構造が完成した状態のこと。
造りによって上棟と呼ぶ状態は異なるが、
鉄筋コンクリート造では屋根部分のコンクリート打設の完了時であることが多い。
さっそく打設の様子をご紹介します!
コンクリート打設用のホースからどんどん生コンが流れ出ていました。
そこに1階立上りコンクリート打設の記事でもご紹介したバイブレータを差し込み、
生コンに含まれる余分な空気や水分を除去→密度の高い生コンにしていきます。
▲職人さんたちが生コンにバイブレータを差し込む様子。
振動によって型枠の隅々に生コンを行き渡らせる効果もあります!
さて、今回は少し視点を変えて生コンクリートを流し込んでいる
スラブ(4階立上りコンなので4階の天井、5階の床となる部分です!)に
見られるあれこれに焦点をあててご紹介していきたいと思います。
▲生コンを打設する前の部分。
白い板のような部分がスラブです。
まずは上の画像で沢山見られるオレンジ色の管から見ていきましょう!
これはCD管(合成樹脂可とう電線管)という電気配管です。
CD管の中には電線や通信ケーブルなどが入っていて、
打設されるコンクリートにこれらの線が接触しないように保護をしています。
▲オレンジ色の管がCD管(合成樹脂可とう電線管)。
打設されるコンクリートから電線などを守ります!
CD管はコンクリート埋設用の配管で、露出配管(露出した状態での配管)はできません。
この管が鮮やかなオレンジ色なのは上記のような配管間違いを防ぐためで、この色で統一されています。
CD管自体はコンクリートの中に埋まってしまうため、完成後では中々見られない存在ですよ。
そして上の画像に見切れている黄色いものはスミポインター、
3階立上りコンクリート打設の記事でご紹介しましたね。
墨出し用にわざと開けてある穴を生コンで埋めてしまわないように、
スミポインターをその穴にはめた状態のまま打設が行われていきます!
▲黄色い筒のようなものがスミポインター。
それでは今回はこのへんで!
次回の更新をお楽しみに!
【完成予想パース】

◇物件詳細
◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら
◇賃貸経営をご検討の方はこちら
◇注文住宅をご検討の方はこちら
◇見学会にご興味がある方はこちら
☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|4階型枠工事(型枠支保工(パイプサポート))
皆さま、こんにちは。
いよいよ新入社員がそれぞれの部署に配属されてきます!
少し緊張もしますが、それ以上にとても楽しみです。
4月は出会いの季節、人との縁を大切にしていきたいものです。

さて、前回は3階立上りコンクリート打設の様子をお伝えしました。
(☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|3階立上りコンクリート打設(コンクリート検査・スミポインター))
今回は4階の型枠工事の様子をご紹介いたします!
現場の様子です。
2階の型枠工事の記事でも紹介した断熱型枠材が敷き込まれていました!
こちらはスラブという、上階の床と下階の天井になる構造体となります。
こちらのスラブは4階の床・3階の天井部分になりますよ!
この後、スラブの上に配筋を行い=スラブ配筋、コンクリート打設へと工事が進んでいきます。
今回紹介したいのはこのスラブの下の部分!
1つ階を下るとこのようになっていますよ。
▲天井の白いところが先ほどのスラブです
この林のようにニョキニョキと生えているものは型枠支保工(パイプサポート)。
その名の通り型枠を支えるために設置するもので、長さの調整も可能です。
▲中ではちょうど職人さんが型枠を固定する作業を行っていました。
パイプサポートの上にバタ角(※)を並べ、
さらにその上に根太(※)を乗せることで型枠を支えます!
上から型枠>根太>バタ角>パイプサポートの順で重なっていますよ。
※バタ角(端太角)
型枠の側面を固めるために使用する約10cm角の角材のこと。
木の種類はスギやマツ、ヒノキなど様々。
※根太(ねだ)
30cm程度の間隔で並べられるもので、上の板を支える役割をもつ。
単管と呼ばれる鋼管パイプが根太として用いられる場合が多い。
▲パイプサポートの上部分。
その上にバタ角と根太、そしてスラブが乗っています。
尚、こちらの型枠支保工は型枠を支えるものなので
上に打設したコンクリートが十分な強度まで硬化した後は取り外されます。
1階の型枠工事の記事でも紹介した通り、打設のための仮設物であるコンクリートパネルも取り外されますよ。
こちらはさらに1つ下の階、既にパイプサポートが外された階の様子です。
後にお部屋となる空間が出来上がっていました!
少しずつですが、建物が出来上がり始めていますよ。
それでは今回はこのへんで!
次回の更新をお楽しみに!
【完成予想パース】

◇物件詳細
◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら
◇賃貸経営をご検討の方はこちら
◇注文住宅をご検討の方はこちら
◇見学会にご興味がある方はこちら
☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|3階立上りコンクリート打設(コンクリート検査・スミポインター)
皆さま、こんにちは。
4月になり、新年度を迎えましたね。
1日に入社式があり、初々しい新入社員たちを見られました。
今一度気を引き締めて仕事に取り組んでいきたいと思います!

さて、前回は3階の型枠工事の様子をお伝えしました。
(☆川崎市中原区の店舗併用賃貸マンション|3階型枠工事(セパレータ・断熱材パット・Pコン))
今回は3階立上りコンクリート打設の様子をご紹介いたします!
上棟(※)となる5階まで「配筋工事・型枠の建て込み」→「コンクリート打設」の流れを繰り返していきます。
前回は配筋工事・型枠の建て込みを行ったので、次はコンクリート打設となります。
※上棟
建物の基本構造が完成した状態のこと。
造りによって上棟と呼ぶ状態は異なるが、
鉄筋コンクリート造では屋根部分のコンクリート打設の完了時であることが多い。
現場の様子です。
現場の入り口では何やら作業が行われていました。
こちらはコンクリート検査の準備でした!
安心・安全な建物を造る上で打設前に生コンクリートの検査を行っています。
現場ではスランプ試験、フレッシュコンクリート試験、塩化物量試験などの試験を行っていますよ。
まず、奥の生コンが山のようになっているのがスランプ試験です。
コンクリートのやわらかさを計測する試験を行っています。
生コンがやわらかいと打設の際の施工性は上がりますが、コンクリートの強度は低下してしまいます。
そのため、コンクリートが適切なやわらかさかどうかを調べる試験を行います。
次に、手前の青い機械を使って行うのがフレッシュコンクリート試験です。
こちらは生コンクリートの空気量を計測する試験となります。
生コンには施工性や耐久性のために微小な空気が入っており、その量がコンクリートの品質を左右します。
空気量が多くても少なくても低品質になってしまうため、規定値かどうか調べる試験を行いますよ。
そして塩化物量試験は生コンをバケツに入れて塩化物量を計測する試験です。
塩化物量が多く含まれていると、鉄筋の腐食や錆を引き起こし、
コンクリートのひび割れや剥落が発生、建物の強度に悪影響を及ぼす可能性が。
これらを防ぐために打設の前に生コンの塩化物量を計測しています。
▲職人さんが手にしているのがフレッシュコンクリート試験用の空気量測定器。
コンクリート打設を行う前に現場で各種検査を行っています!
現場以外で行われる検査もありますが、
そちらの検査については弊社の公式YouTubeに動画がありますので、ぜひご覧ください!
では、打設の様子を見ていきましょう。
取材当時、柱となる部分へ生コンクリートが流し込まれていました。
こちら、2階立上りコンクリート打設の記事でも紹介した柱配筋の部分です。
その時に『ブラッシングしていた柱の部分は上階にもつながっている』と
紹介しましたが、このように上の階につながっていますよ。
上の画像で職人さんが手をかけている黄色い筒のようなものがありますね。
こちらはスミポインターといいます!
このポイントがある部分、実は穴が開いています。
これは後の墨出し(※)のためにわざと開けられたもので、
この穴から下の階にある基準墨(※)の糸を上の階に移すことで、
下の階と同じ場所に墨出しを行うことが可能になるんです!
※墨出し
設計図を実寸で地面に書き出す作業のこと。
使部材の取り付けや仕上げ作業のために、墨糸で下地面などに印を付けていく。
※基準墨(きじゅんずみ)
軸線の基準となる墨のこと。元墨(もとずみ)ともいう。
打設自体は今まで通り、生コンを流し込んで、均して、完了となりました。
そして打設完了後の様子がこちら!
職人さんたちの手によって綺麗に仕上げられていました!
それでは今回はこのへんで!
次回の更新をお楽しみに!
【完成予想パース】

◇物件詳細
◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら
◇賃貸経営をご検討の方はこちら
◇注文住宅をご検討の方はこちら
◇見学会にご興味がある方はこちら